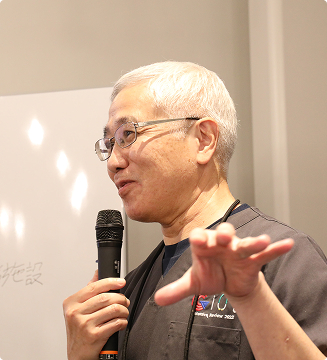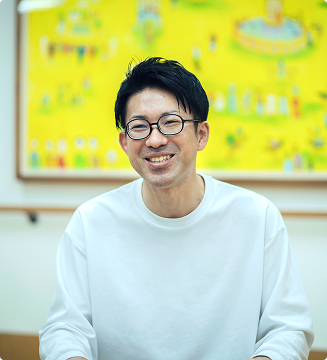HMW総診 プロジェクトメンバーの声
病気ではなく「人」に向き合う。
そんな医師を、HMW総診は育てたい。
指導医
八戸 敏史
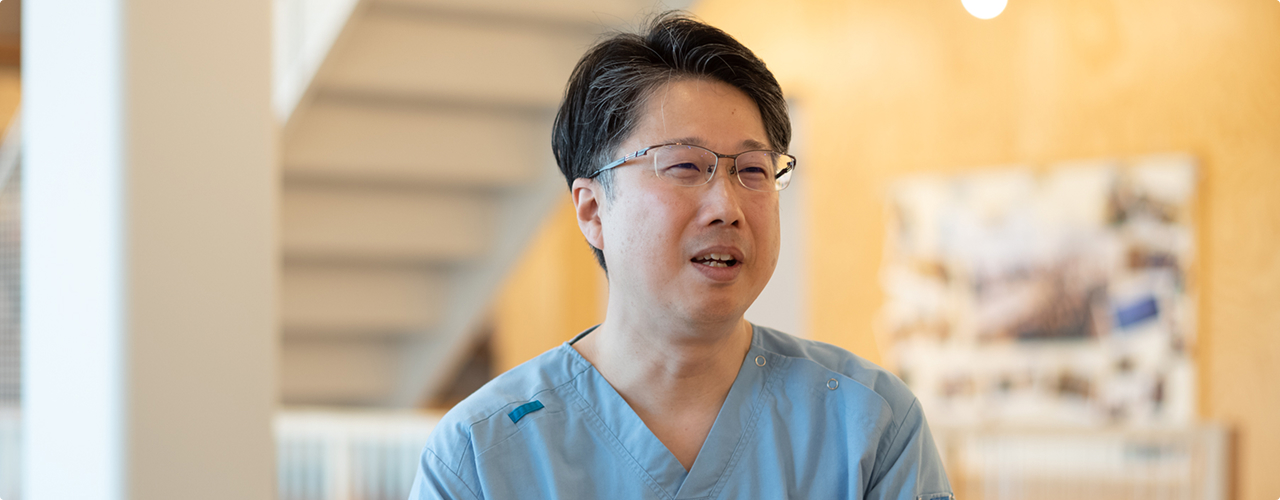
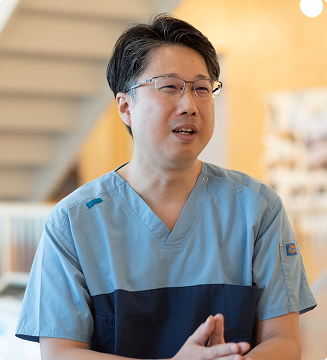
これまでのキャリアを教えてください
私は、当時スーパーローテート方式を先駆的に導入していた独立行政法人国立病院機構(NHO)東京医療センターにて初期臨床研修を受け、プライマリ・ケアに必要な基礎知識、技術、そして何より重要なマインドを学びました。その中で、多様な疾患カテゴリーに対応する呼吸器内科に魅力を感じ、国内有数の呼吸器病院であるNHO東京病院で専門研修を積みました。大学病院ではなく、地域に根ざした一般病院での診療を希望した背景には、「患者さんの最も近くにいたい」という思いがありました。しかし、臨床経験を重ねる中で、「より多くの患者さんの未来に貢献したい」という気持ちが芽生え、専門医取得後に研究の扉を開けることになりました。順天堂大学および慶應義塾大学でがんの基礎研究に従事し、その後は米国ハーバード大学・マサチューセッツ総合病院にて博士研究員として研鑽を積み、CellやNature関連誌などに成果を報告する機会にも恵まれました。帰国後は順天堂大学にて、教育・研究・臨床の三本柱にphysician-scientistとして取り組みながら、総合的な視点で後進の育成に努めてきました。呼吸器疾患の特性上、急性期と慢性期の切り分けが困難なことが多く、大学病院であっても診断から治療、そして時に看取りまで、主治医として一貫した関わりが求められます。こうした経験を通じて、医師として「人」を診る姿勢を大切に、自身の診療と後進の育成に取り組んできました。
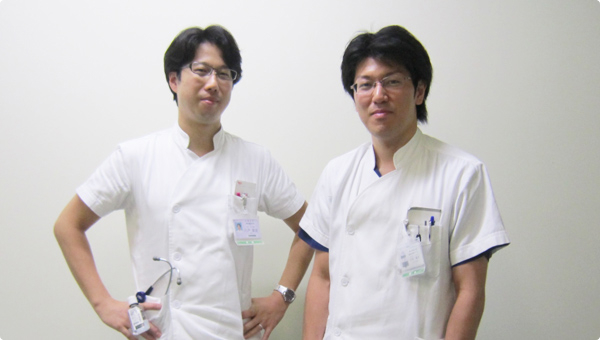
12年前日本で後輩と

ハーバーード時代ボストンでのキャンプ
平成医療福祉グループはどんなグループですか?
大学病院での診療を通じて、私は年々進行する高齢化の影響を強く実感してきました。急性期や先進医療の重要性は言うまでもありませんが、今後ますます必要とされるのは、慢性期を中心とした包括的な医療・ケアであると感じ、2024年に平成医療福祉グループへ参画しました。このグループの大きな魅力は、明確な理念と方向性を持ちつつ、多様なバックグラウンドや世代の職員が、立場にとらわれずフラットに意見を交わせる風土があることです。そして何より、私がこれまで一貫して大切にしてきた「人を診る」という姿勢が、現場レベルで深く根づいていることに、強く共感し、感銘を受けました。疾患単位ではなく“生活単位”で患者さんに向き合う視点、そして医療・介護・福祉が垣根なく連携するケア体制は、私が思い描いてきた理想に非常に近いものでした。また、これまでのキャリアで培ってきた「俯瞰的な視点」も、地域包括ケアや多職種連携が重視されるこの環境の中で自然に活かされ、日々大きなやりがいを感じています。現場には学びの機会が豊富にあり、若手職員の熱意やエネルギーからも日々良い刺激を受けています。「臨床の質」と「人間としての尊厳の尊重」が高いレベルで両立しているこの環境の中で、これまでの経験を活かしながら、次世代の育成、地域医療の質の向上、そして地域社会が抱える課題の解決に貢献していきたいと考えています。
研修を検討されている方へメッセージ
患者さん自身に「急性期」「慢性期」といったラベルが貼られているわけではありません。それはあくまで医療側の制度的な視点にすぎず、患者さんは常に“その人”として、変わらず存在し続けています。そうした本質的な理解と関わり方を大切にしたい方にとって、HMW総診はきっと大きな学びの場になるはずです。HMW総診では、総合内科、小児科、救急科、整形外科、精神科、緩和ケアなど、プライマリ・ケアに必要な基礎をしっかりと身につけられるのはもちろん、制度設計や政策提言に関わる厚生労働省への出向、公衆衛生や社会課題に取り組む実践の機会も用意されています。多様な領域を横断しながら、実践を通じて「医療の社会化」を体現できる、非常にユニークな環境です。私たちが目指しているのは、医療と社会の接点に立ち、「人に優しくできる医師」、「人の話をきちんと聞ける医師」、そして「医療の枠を超えて社会とつながれる医師」です。私自身の進路においても、素晴らしい指導医との出会いが大きな転機となりました。人との縁には、ときに運命のような力があると感じています。HMW総診でも、きっとそんな新たな出会いがあると確信しています。このグループには、多様な価値観や働き方をもつ仲間がすでに多く集っています。自分らしく、前向きに、そして楽しく働ける環境があります。ぜひ私たちと一緒に、これからの医療と社会を共に創っていきましょう。